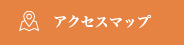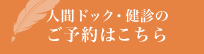肘部管症候群
肘部管症候群の原因

肘関節は上腕骨(肩~肘の間の骨)と橈骨・尺骨(肘~手首の間にある2つの骨)の3つの骨から構成され腕の屈伸(曲げ伸ばし)・回旋(腕をひねる)の動きに対応しています。
肘関節の内側には、肘部管(トンネル)を走行する神経(尺骨神経)があり、主に小指、薬指、手の側面に対しての動きや知覚を与えています。
肘部管症候群は、この尺骨神経が圧迫されたり引っ張られたりすることによって引き起こされます。
原因として、手や肘を酷使する仕事や日常生活のケガ・スポーツ外傷による骨折、加齢による骨の変形、 ガングリオンなどの腫瘍による神経の圧迫により痛み・知覚異常・筋力低下などの症状を引き起こします。
肘部管症候群の症状
手の小さな筋肉の大部分は尺骨神経がつかさどっているため以下のような症状により日常生活への支障が出る可能性があります。
初期段階としては、
- 小指・環指(薬指)の手のひら側のしびれ・痛み
進行してくると、
- 母指(親指)・示指(人差し指)を開いたり閉じたりする筋肉の一部が萎縮(筋肉がやせる)
- 小指・環指(薬指)の麻痺による変形(かぎ爪変形)
- 手の筋力低下(握力低下)
- 箸を持つなど手の細かい動作が困難
肘部管症候群になりやすい人
- 野球や柔道など肘に負担がかかるスポーツを行う方
- 加齢による肘の骨の変形
- 骨折、脱臼などの外傷による肘の骨の変形
- 力仕事など手や肘を酷使する仕事
- 腫瘍(ガングリオンなど)による神経への圧迫
- 交通事故によるケガ
肘部管症候群の検査
診察にて、上肢(上腕~手指)の痛み・しびれ・変形などの範囲、筋肉の萎縮の有無、どのような動きで痛みを感じるのか(チネルサイン・肘屈曲テストなど)を確認します。画像検査では、レントゲン検査により肘の骨の変形の有無を確認します。MRI検査ではガングリオンなどの腫瘍が疑われる場合に行います。
肘部管(ちゅうぶかん)症候群の治療
治療として、一般的に保存療法と手術療法に分けられます。
保存療法
保存療法として、上肢(上腕~手指)の痛み・しびれなどの症状が強い場合は、日常生活では肘に負担をかける動きをしないように安静を基本とし、しびれや痛みなどの炎症を抑えるために湿布や内服薬にて経過をみます。
手術療法
手術療法としては、症状が進行しており保存療法で効果がみられない場合や腫瘍(ガングリオンなど)による圧迫、骨折・脱臼などの外傷が原因で、痛み・しびれなどが増強し日常生活に支障がある場合は手術が必要となります。
肘部管症候群にお困りの方は、かかりつけの先生にご相談下さい。
背中の痛みについて(内科領域)はこちらをご覧ください。